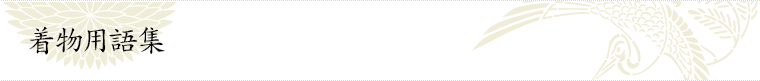- 八重山上布-やえやまじょうふ
- 沖縄県八重山地方、石垣島で生産される平織の麻織物。さらさらの肌触りで軽く涼しい布なので、夏向きの素材となっている。
- 矢絣-やがすり
- 矢羽根をモチーフとした絣文の織物。弓で射た矢は戻らない、まっすぐに突き進むことから、縁起柄とされている。

- 八つ口-やつくち
- 着物の脇あけのことで、身八つ口ともいう。女性と子供の着物だけにあり、袖付けと脇縫の間を縫い合わせずにあけた部分を指す。
- 柳絞り-やなぎしぼり
- 絞り染の一種で、滝絞りとも言う。しだれ柳のような柔らかさのある線文を表した絞。
- 矢羽根-やばね
- 矢羽根の文様のこと。矢筈とも呼ばれる。
- 山藍-やまあい
- トウダイグサ科の多年草。山藍を布に摺りつけて染めること、および染めたものを、山藍摺りという。
- 大和絣-やまとがすり
- 奈良県大和高田市周辺で生産される木綿の白絣。天保年間(1830~1843年)、絣模様のデザインと染めのよさで人気があった。
- 山繭-やままゆ
- ヤママユ科の蛾のこと。この繭からとった糸を山繭糸という。
- 山繭縮緬-やままゆちりめん
- 光沢があり、丈夫な山繭糸を縞糸にして縮緬に織ったもの。
- 山道-やまみち
- 山道模様のこと。くねくねと曲がっている山道を文様に表したもの。
- 結城紬-ゆうきつむぎ
- 茨城県結城市と栃木県小山市周辺で生産される紬織物。糸を紡ぐ、絣くくり、地機で織るの三つの工程が、重要無形文化財の指定を受けた。
- 友禅-ゆうぜん
- 日本を代表する文様染で、友禅染のこと。色彩的で精巧な染模様を指し、日本の染物の代名詞ともなっている。
詳しい情報は「名古屋友禅」ページをご覧ください。 - 友禅縮緬-ゆうぜんちりめん
- 多色多彩ではなやかであり、縮緬地に友禅模様を型染したもの。女性の着物や七五三などに用いられる。
- 湯帷子-ゆかたびら
- 入浴のとき、または入浴後に着る単(ひとえ)のこと。湯に入るときに用いる麻の着物を指す。
- 雪晒-ゆきざらし
- 積雪の上に麻織物や竹細工などを並べて漂白すること。白地の白が冴え、染料の色が鮮やかになる。
- 雪輪-ゆきわ
- 雪片の六角形をモチーフに円形にデザインした古典的で品格のある文様。
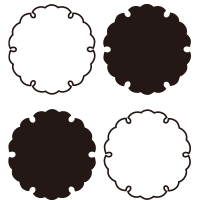
- 湯通し-ゆどおし
- お湯の中に生地を入れて、糊を落とすこと。後で湯のしをして、幅を調整する。
- 湯熨-ゆのし
- 熱した湯気の中に生地をくぐらせ、シワ伸ばしや、幅の調整をすること。
- 木綿-ゆふ
- 古文献や万葉集にでてくる木綿で、楮(こうぞ)や麻をさらしたもの。真綿とも呼ばれる。
- 湯巻-ゆまき
- 平安時代に、貴人が入浴の際に身を包んだ衣。ゆもじ、下裳とも呼ばれる。
- 弓浜絣-ゆみはまがすり
- 鳥取県の弓ヶ浜半島で生産されている絣の綿織物。手紡ぎのざっくりとした素朴な風合いが好まれている。
- 楊枝糊-ようじのり
- 友禅染で防染に使われる糊置き技法。糊を棒の先につけ、垂れ落ちてくる糊の線で糸目糊を置く方法。
- 揚柳縮緬-ようりゅうちりめん
- 緯糸に強撚糸を使い、縦方向に柳の葉のようはシボを表した縮緬織物。
- 緯糸-よこいと
- 織模様を表したもので、緯方向に通っている糸のこと。
- 緯総絣-よこそうがすり
- 緯糸全部に絣糸を用いて織られている緯絣の絣織物。緯絣に比べて込み入った柄、複雑な柄の表現ができる。
- 緯錦-よこにしき
- 経糸で文様を織り出した経錦に対し、緯糸で文様を織り出した錦織の一種。
- 緯絽-よころ
- 絽の一つで、絽目という透き間が横方向に現れている織物。通気性がよく、夏物に用いられる。
- 四つ身-よつみ
- 着物の裁ち方の一つ。前身頃をつまみ縫いして衽をつくる。
- 米琉-よねりゅう
- 米沢琉球紬の略。品質が琉球紬に似ていることからこの名称が付いた。
- 撚糸-よりいと
- 特別の地風を出すために糸に強い撚りをかけたもの。または、単糸を数本合わせて撚った糸の総称。
- 蹣跚縞-よろけじま
- 波のような線の縞模様。曲線の縞が曲がってよろけたように見えるため、この名称が付いた。