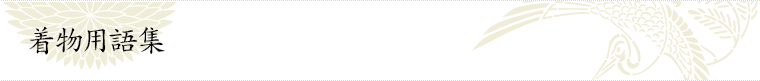- 羅-ら
- 薄く織った絹の布。目の粗さから、通気性に富み、夏の織物として用いられる。「うすぎぬ」、「うすもの」とも言う。
- ラミー
- 麻の一種で、ラクサ科の多年草であるカラムシの大形のものから採れる繊維。漂白して上布を織るのに用いる。
- ラメ織-ラメおり
- 金銀のような金属系や、金属的な光沢のある糸を用いた織物。御召や、箔として染加工に用いる。
- 利休茶-りきゅうちゃ
- 緑がかった薄茶色。緑を帯びた色には、利休色、利休白茶、利休鼠など「利休」がつく色名が多くついている。
- 琉球藍-りゅうきゅうあい
- キツネノマゴ科の半灌木。沖縄伝統の芭蕉布、紅型、宮古上布、琉球絣などの染織技法に琉球藍が用いられる。
- 琉球絣-りゅうきゅうがすり
- 琉球産の絣織物の総称。流水・井桁(いげた)・つばめ柄などがあり、宮古島の紺絣、八重山の白絣などが知られる。
- 流水模様-りゅうすいもよう
- 流れる水を文様化したもの。着物の文様に古くからも用いられ、留袖などの裾模様に多く用いられる格調高い柄となっている。
- 竜紋-りゅうもん
- 羽二重に似た厚手の絹織物。織り目は斜めで地は厚い。紋付や羽織、帯地などに用いた。
- 裲襠-りょうとう
- 帯を締めた上に打ち掛けて着る、丈の長い小袖。「かいどり」ともいい、花嫁衣裳に用いる。
- 両面織-りょうめんおり
- 表裏を違う色や柄で同時に織り進めた生地のこと。経糸緯糸ともに二重にした二重組織の織物。
- 両面仕立て-りょうめんしたて
- 着物の表と裏を毛抜合わせに仕立て、両面どちらも使えるように仕立てたもの。
- 両面染-りょうめんぞめ
- 布地の表と裏に、異なった文様や色を染めたもの。表裏同じ色柄で染めることも、両面別の染めをすることもできる。
- 綸子-りんず
- 経糸緯糸とも生糸の無撚糸を用いて、繻子織りの表と裏で文様を織り出した絹の紋織物。
- 絽-ろ
- 夏の着物を染める白生地で、平織りとからみ織りを組み合わせ、経糸と緯糸を絡ませて透き目を作るように織る。
- 﨟纈-ろうけち
- ろうけつ染にあたる古代染色方法の一つ。蝋を防染剤に用いる模様染め。
- ろうけつ染-ろうけつぞめ
- 溶かした蝋で布地に模様を描き、染色後に蝋を取り除く染法。蝋をしみこませた部分が白く染め残る性質がある。
- 六尺帯-ろくしゃくおび
- 長さが六尺(2~3メートル)の兵児帯。
- 六尺通し-ろくしゃくとおし
- 六尺通し柄の略。お太鼓のたれ先から胴まで、二重に巻いた寸法に文様のある帯のこと。
- 路考茶-ろこうちゃ
- 暗い黄みがかった茶色。染色記事や浮世絵美人の衣裳に多く見られた。
- 絽刺し-ろざし
- 絽織の透き間へ数段に糸を刺して文様を表す技法。糸は、特別な絽刺し糸を用いる。
- 絽縮緬-ろちりめん
- 普通の縮緬地の中に、捩り組織の透き間を織り出したもの。盛夏の前後の季節に染下生地として広く用いられる。